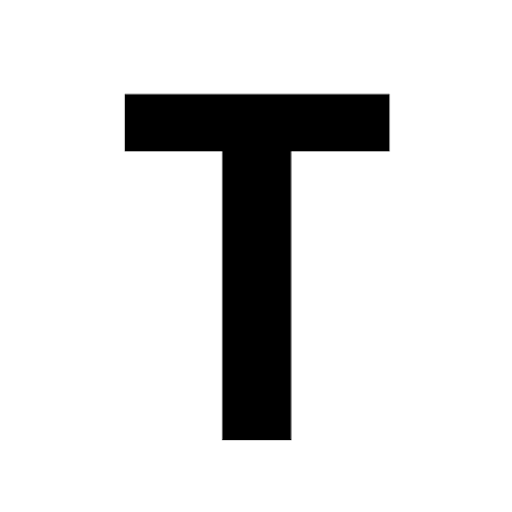石の上にも三年は残念である。
ブラックな精神論が蔓延る現代において根性とか忍耐力とかの象徴的ワードと化しています。
「とりあえず3年」みたいな話はそこら中に溢れているのって、多分石の上にも三年に引っ張られた結果じゃないかと。
なんだか不憫に思えて仕方ないこのことわざをもう一度見つめ直したい。そんな思いが今日のテーマです。
ざっくりまとめると、
- 石の上にも三年は忍耐強く継続することの大切さを説くことわざであって、ともかく我慢しろの精神論まるだしの意ではない
- 特に仕事で根性論の象徴として残念な扱われ方をしている気がするのでやめましょう
- 一方で、正しく認識された上でコツコツ継続することを説くこのことわざは残念だとする意見がある
- 確かに、目まぐるしいスピードで変化する現代で無心で継続しているだけでは時代に置いていかれるという考えには説得力はある
- とはいえ、忍耐強く継続することによって成長ができるし、適応力アップにつながる事実を見逃してはいけないと思う
- 「無理に耐える」か「さっさとやめる」の2択で物事考えるのではなく、適宜バランスを取るというありきたりな考えが、その実王道なのだと思う
- 石の上にも三年に限らず、言葉の本質をよく考えると為になることって多いですよね
石の上にも三年は残念な扱われ方をしている
石の上にも三年という言葉が残念な扱いを受けているような気がします。特に仕事で。
時として退職者に対して「根性が足りない」「三年は我慢しろ」的な使い方をする場面を観測します。私も幾度となく体験しています。
実際はそんな精神論的な話ではなくコツコツと継続することが成功につながるという意味のことわざです。
三年という期間も物の譬であって「3年」という意味ではありません。人や状況によって継続の花が開くまでの期間はそれぞれです。
事前に提示された労働条件と違う、バイオレンスな職場環境、これって違法では、、、?みたいな会社であれば三年と言わず三秒で退職者が出ても何らおかしくありません。
あくまで私の経験上ですが、こういった会社は石の上にも三年を誤用した根性論を展開してくる傾向が高いです。
この辺り、正しい認識と活用によって石の上にも三年の社会的地位が回復することを願うばかりです。
一方で、石の上にも三年自体が残念かもしれない
一方で、正しく石の上にも三年を認識した上で、このことわざに否定的な意見があるのも確かです。
「変化が遅く情報量の少ない時代では通用しても、あらゆるものが凄まじいスピードで変化し次々に技術や情報が刷新される現代では通用しない。自分のキャリアプランや相性を考えず黙々と仕事を継続するだけでは成長できず時間の無駄。」
といった論調が多いように思います。
なるほどなぁと思う部分は多々あります。
個人的かつ突然な話で恐縮なのですが、プログラマーの人たちってカッコよくないですか?
最先端の技術や知識、ゲームやアプリを作る今時の仕事、映画に出てくる凄腕ハッカー、現代の新しいサービスを生み出す錬金術師じゃん!!というのが私の持つイメージです。
残念ながら入り口の段階で私には理解が追いつかなかったので目指すことすらできませんでしたが、所謂IT系と呼ばれる仕事を生業としている人が昔から凄くカッコいい存在と認識していました。
ところがです。AIの出現によりプログラマーは不要というニュースを目撃しました。
実態を把握しているわけではないですが、あの最先端の仕事と思っていたプログラマーが淘汰される可能性なんて想像すらしたことがありません。
変化のスピードが以前にも増して加速していくのは間違いないでしょう。
スキルが求められるプログラマーですら仕事内容によっては淘汰される可能性があるわけです。これが単純作業やスキル不要な仕事であれば殊更不要扱いされるのはあっという間でしょう。
何も考えずただただコツコツと続けていくだけでは仕事が難しくなるかもしれないという意見になるほどなぁと思ったのでした。
もとい、石の上にも三年は残念ではない
とはいえ、石の上にも三年は残念という意見に疑問がないわけではありません。
1つ目が、なぜ今の仕事を与えられているのかの視点の欠落。
成長が期待できない仕事とは未熟でもできるという意味です。時間さえ掛ければ完了できます。
上司が何も考えずに仕事を振っているのなら石の上にも三年が残念理論は成り立ちますが、もしかしたら自身のコツコツ積み上げた実績や能力が不足しているのかもしれません。
もし単純な実力不足が原因ならば、むしろ継続する方が成長のチャンスですし、その事実に気付かず環境を変えても根本的な解決につながりません。
2つ目が、その業務が仕事全体の要素であるという視点の欠落。
明らかに無駄や前時代的な業務、不本意な仕事なら話は変わりますが、その業務は少なくとも仕事全体にとって必要だから存在しています。将来的に人からAIに取って代わられるとしても、やる人(機械)が変わるだけで業務そのものがなくなるわけではありません。
AIによって私でも簡単なアプリを作れるようになりましたが、なぜ動くのかは私にはさっぱりわかりません。少なくとも仕組みを理解できる人の製品でないと使いたくならないのでは?と思います。
3つ目が、各要素の関連性という視点の欠落。
仕事(会社)は一つの業務で構成された単純なものではなく複数に跨り、これらのつながりを無視すると上手くいかないことがよく起こります。
例えば、営業が取ってきた仕事に開発が間に合わないと回答するなんてのは会社あるある話ですが、双方ある程度妥当な理由を持っているものです。
競合他社と納期面で差別化したい営業側、製造キャパにバッファを持たせたい開発側、実際には擦り合わせる手立てはあるのですが、一義的な見地から意見をぶつけ合うとまとまるものもまとまりません。
乱暴な例示ですが、自分は求めていない、相性が悪いと思える業務でも一通りこなして思考の切り口を増やすことに意味はあるんじゃないかなぁと思います。
4つ目が、適応能力という視点の欠落。
環境や自身の成長によって仕事との相性に変化が生まれる、適応する可能性はあります。
クソみたいな環境や人に合わせる必要は1ミリもありませんが、自分との相性の良し悪しだけが問題だった場合、コツコツ継続するうちに心境や景色が変わったなんてことは存外起こります。
自分の得意分野だからといって、全て自分が把握しているなんて限りません。多分無理です。
もしかしたら自分の未知の能力を見逃してしまうかもしれません。
要は偏りすぎないようにしたいということ
もちろん先に挙げた疑問点は当たり前だったり極論だったり論理の飛躍だったりするので、石の上にも三年が残念と考えている人はわざわざ言及していないだけでしょう。
本当に必要な能力を獲得するにはコツコツ継続が大事であり、本当に成長を阻害する環境や無駄な仕事を我慢してやる必要はないということを言いたいのだと思います。
私自身、何でもかんでも忍耐強く継続していればいいなんて思っていません。要は偏りすぎが良くないなと考えているだけです。
時間には限りがあって、返ってこなくて、待ってはくれない大切なものです。ただただ自分が犠牲になるだけの我慢なんて真っ平ごめんです。
独りよがりに無駄と断じるような傲慢さは望んでいません。ほんの少しの間で自分の可能性を否定するような真似をしたくありません。
石の上にも三年に限らない話ですが、言葉の本質を考えるとライフハックにつながるんじゃないかと思う今日この頃。せっかくの機会に言葉の理解を改めて深めたいと思う次第です。
以上、最後までありがとうございます。