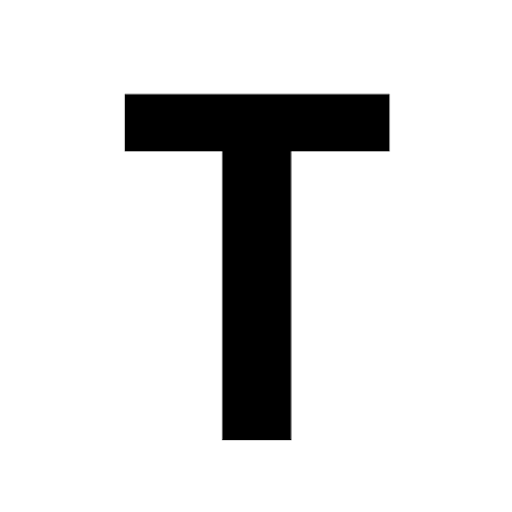人との会話が上手くない。何かと会話で衝突してしまう。
そんな時には、どんな会話もビジネスライクで割り切ってしまうのも手ではないかと思います。
ざっくりまとめると、
- 「人は他人の話をきいていない」というのは概ね事実
- 会話に自分が期待する反応を求める傾向が強く、結論ありきの会話になりがちなのが理由
- 結果、会話の円滑さは会話の中身よりも期待通りかどうかに依存しやすい場面が出てくる
- ところが、相手の期待を読み取るには多大なコストが掛かる上に、完璧に把握するのは無理
- とりあえず会話を弾ませたい時には、相手の意見を否定せず、こちらの意見は簡潔に述べるだけといったビジネスライクな会話で大雑把に相手の期待に沿うことができる
- ただし、相手の期待に応えようと集中しすぎると迎合するような形になって逆効果なので、応える期待は会話そのものに留めるべき
- 一方、我が道を貫くスタイルも存在していて凄みと潔さを感じさせるが、その裏には強い覚悟と周囲にもメリットがある相互関係を築いていることは忘れてはならない
- 個人的には、会話から学べることは沢山あるので、できる限り会話を弾ませられたらいいなと思います
会話なんて結論ありき
唐突に皮肉っぽい話で恐縮なのですが、「人は他人の話を聞いていない」というのは概ね事実だと思います。
大抵の会話は各々結論ありきで進めていて、相手の話ではなく自らが期待する反応を待っているところがあるからです。
質問なんかはわかりやすいです。期待する答えが必ずあって、それは単純に解決策や方法かもしれませんし、質問者に都合の良い答えかもしれません。
相談も実際のところ意見なんて求めていません。単に話を聞いて欲しいだけだったり、自分の意見への同意が欲しいだけだったり、他人の意見を求めていないなんてザラです。
議論(特にルールを定めていない時)なんか、自分の意見にどうしても愛着があるので会話が盛り上がるほど自分の意見に執着しがちです。
なんなら、普段の何気ない会話でも、打ち解けたい、聞いて欲しい、沈黙を避けたいといった結果を期待しています。
もちろん純粋に他人の意見を求める人はいますが、自分の期待とは異なる結果をポジティブに受け止められる人はなかなかのメンタル強者で、かなりのレアな存在だと言えます。
ほとんどの人は期待する結果を望みますし、それはごくごく当たり前の感情です。
人は思った以上に他人の話は聞いていないのは、ある程度やむを得ないのかもしれません。
期待外れの結果なら会話がぎこちなくなるのは仕方ない
で、期待外れの反応が返ってくると会話の流れはぎこちないものになります。
期待通りの答えでなければ同じ質問を繰り返されるかもしれませんし、同情や同意が欲しいのに反論や正論をぶつけられればムッとされるかもしれません。
まー相手の心理からすれば当然と言えば当然なのでしょうが、こちらにはこちらの結論があるわけで相手の期待通りになるとは限りません。
本音と本音だけで会話すれば程度の差はあれ会話の流れがぎこちない瞬間はちらほら出てきます。
とはいえ、ほとんどの人が一人で生きているわけではなく他人と関わりながら生活しています。
当然のことながら他人への気遣いは必要で、会話も相手の期待を読み取りつつ進めていかなければいけない。
ところがですよ。会話ってテンポも大事じゃないですか。話が盛り上がると感情の起伏も生まれますよね。急な話題の転換なんかも。
冷静に相手の期待を読み取るにはそれなりのリソースが要求されるのに、会話が進むにつれてリソースがガリガリ削られる要因が増えてくる。
「会話が上手くいかない」「軋轢が生じる」となったらストレスになる。
当たり前のように会話をしていますが、リソース管理とストレス管理を要求される実は高度な技術なのでは?と思えて仕方ありません。
にもかかわらず人間沈黙がどうも苦手です。特にそれほど親しくない人と同席すると余計に辛い。なんなんですかね、この特性。
お互いよく知らない同士、沈黙の時間を極力減らすべく会話をスタート。しかし、お互いの基本情報から手探りな状況。想像だけでお腹痛くなりそうです。
仕事などテーマが限定できても十分大変ですし、フリートークならさらに負荷は激増します。沈黙が気にならないような気の置けない友人のありがたみを凄く実感する瞬間です。
といった具合に、会話は我々と切ってもきれない関係にありますが、会話そのものに上手くいかない要因が散りばめられていますし、我々の特性がキツい場面を作り出すように働きかけてくるトンデモ仕様になっています。
どうにも上手く会話を進められないということがあっても何ら不思議ではありません。
ビジネスライクな会話は案外万能
というわけで、会話は何かと大変な行為ですが、とりあえず会話の難易度を下げたい。上辺だけでも会話をスムーズにしたい。そんな時には一度原点に立ち返ってみるといいかもしれません。
それは、「人は他人の話を聞いていない」という事実。
極論、こちらの主張や意見なんかどうでもいいわけです。相手の期待を読み取り、それに沿うだけで会話は自然と転がっていきます。
相手の期待を読むことも難しく考えなくて構いません。本当に期待を読み取るなんてまず無理です。人が何考えているかなんてわかりっこないので。
ですから、基本的にやれることは「相手の話を否定しないこと」くらいなもの。なんだけれど、これだけで結構な期待にふんわり沿えます。自分の主張を展開したい。愚痴を聞いて欲しい。間を繋ぎたい。とかですね。
ちなみに、同意はしなくても良いです。考え方は無数にあって同意できるかはわかりませんし、とりあえずで同意すると碌なことになりません。
否定しないだけでも期待外れとまではなりませんから、人の道外れるような考えでもない限り否定しなければ十分です。
また、相手に水を向けられ自分から発言する場合も難しく考えず、簡潔に意見を述べたり、質問に回答したりすれば大丈夫です。
さらりと意見を述べるに留めておけば相手が違う意見でも「そういう考えもあったのか」と会話の中心を相手に置き換えやすくなります。
単純に情報が欲しいものだった場合も一定の期待には応えられています。
で、この会話方法って、まんまビジネス会話だと思うんですよ。
限られた情報から会話のきっかけを掴むとか、相手のニーズを読み取るべく話を引き出そうとするとか、言うべきことはあるけれど自分の話だけだと上手くいかないとか、似ている部分を挙げれば枚挙に遑がありません。
ビジネスライクな会話って成果という目的がはっきりしている分、相手の話や期待を引き出すことに集中しやすいです。
まずは会話を弾ませたいという点において良いお手本なんじゃないかと思います。
もちろん、ビジネスライクな会話は日常会話だと冷たい印象を持たれるのでは?という懸念はあります。
だけど、普段の関係性って会話だけで築くものでもないのかなと。日頃の立ち振る舞いの積み重ねで出来上がるものなのかなと。実際、仕事関係でも苦難を共に乗り越えた人たちとは、ただの取引先や同僚以上の付き合いになるってことあるじゃないですか。
会話を上手く進めるきっかけとしてビジネスライクな会話を取り入れる試み、案外悪くないと思う次第です。
期待通りの会話は迎合とは違う
何事もやりすぎは良くないものです。
期待を汲み取ろうと相手に集中しすぎて迎合のようになってしまうとよろしくありません。仕事なんかで成果を出そうと相手側に寄り添いすぎて失敗してしまうケース、あれに似ているかもしれません。
会話を弾ませる相手の期待とは、「話を聞いて欲しい」とか「情報が欲しい」とかそのくらいのものです。会話単体、会話そのものから得られる成果とも考えられます。
会話の中身に現れる期待、会話と関係なく相手本人に内包される期待まで考えるのはやりすぎです。狙ってやるなら話は別ですが。
相手によっては便利な人扱いされるかもという心配はあるので注意したいところです。
我が道を直走るのも凄いこと
会話の手間や心配事を考えると、思うがままに話をする選択を考えたくもなります。
もちろん、それも選択肢の一つです。世の中、多少の軋轢なんて気にせず圧倒的パワーで周囲を巻き込める人は確かにいて、覚悟を持って我が道を直走る姿には凄みと潔さを感じずにはいられません。
ただし、声がデカいだけの人と混同してはなりません。
声がデカいだけの人も一見して、我を通して周りを巻き込んでいるように見えますが、関わるくらいなら勝手にさせるてる方がマシと考えられているだけです。
一部のコミュニティ内でしか成立せず、他のコミュニティへ行くこともできません。そして、いずれは受け入れてくれていたコミュニティ内には自分以外誰も残らなくなってしまうでしょう。
我を通すには強引さがありながらも、そのパワーに周囲も助けられているという相互関係はマストなんじゃないかなと。
会話というコミュニケーション手段一つとっても選択肢は無数です。何がベストな選択なのか、人それぞれ考えは違うでしょう。
私は会話のおかげで新しい知見や気付き、自分の弱点など多くのものを得られるなぁと思っているので、できるだけ会話を弾ませたいと思う次第です。
以上、最後までありがとうございます。