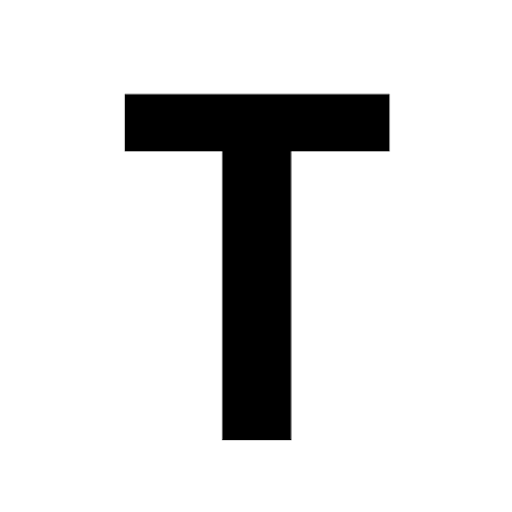私の経験では論破って使える!!と感じた記憶ってないんですよね。
ざっくりまとめると、
- 普段生活していて論破って意味があるのか疑問に感じていて、その理由は大きく2つ
- 一つ目は、絶対的に正しい主張が存在しない限り論破は成立しないのでは?という疑問
- 二つ目は、仮に論破できるとしても、感情的な隔たりが本来の目的達成の妨げになるのでは?という疑問
- テレビやYouTubeで見かける議論はショーの一部であり、論破後の展開は想定していない。一方日常の議論は先の展開があり別物である
- 日常の議論で意見をぶつけ合う時は中心に課題を据えて進めると、直接的な否定は生じないし、感情的な対立も起こりにくい
- 議論する相手は言い負かすべき存在ではなく一緒に課題解決をする存在で、負かさなきゃいけないのは課題
論破って意味あんの?
論破とは、「相手の主張を否定し、自分の正しさを証明すること」「言い負かすこと」という意味です。
SNSでは少しフランクな使われ方も見られますが、根底には同じ意図があるように思います。
というわけで、言語的な意味はもちろんある、、、ではなくて、問題は普段の生活で論破する意味ってあんの?という点です。
この点に関していうと、個人的に2つ疑問があります。
一つ目が、絶対的な正しさというものはあるのか?というもの。
我々が主義主張を展開する時は、専らルールや常識を基にして論理を組み立てます。
で、このルールや常識が普遍的に正しいものって、少なくとも私は思いつきません。そうでなくても前提条件でなんぼでも変わってくるんじゃないかとも思います。
例えば、アリストテレスの三段論法で有名な「人は皆死ぬ」。まさに普遍的な法則と言えるでしょう。
他方、「思い出の中で生き続ける」「忘れ去られた時が死だ」という死生観。人の記憶に残り続けるような偉人であれば、ある意味半永久的に死は訪れないことになります。
この2つを議論した時に一方が論破するって難しいんじゃないでしょうか。
仮に、一般的に生物学的死が前提じゃないのかと主張しても、それこそが前提が変われば主張も変わる可能性を示していますし、その前提を置く絶対的な正しさを示さなければなりません。
誰か第三者がお題を決めて議論するゲームでもない限り、人のルールや常識は無数に存在していて、さらにそれを完全に否定するのは難しいんじゃないかなぁと。
というわけで、一見論破したように見えても、よくよく考えると絶対的に正しいのか?論破って本当に存在するのか?という疑問が残ります。
二つ目が、仮に論破というものが存在するとして、その後どうするの?というもの。
まず、なぜ議論をするのか、特に日常生活で、というのを考えた時に思うのが、方針を絞り込み行動を一致させる為というケースが多いと思います。
この時論破を試みる理由は、論理的な正しさを示し納得感を持って行動してもらう為なのかもしれませんが、多分逆効果。
論破された側、つまり否定された側が良い感情を持つ可能性は低いです。
完全に自分が悪いから怒られた時ですら素直になれないくらいです。人間自分を否定されるって割ときつい。
なので、論破できたとしても、相手が期待通りに行動してくれるかはわかりませんし、したとしてもパフォーマンスは落ちるかもしれません。
また、論理的に正しければ強制的に動かすことができるという考えがあるかもしれません。
しかし、強制力は論理ではなく、その組織のルールによって働きます。
強制できるなら、そもそも議論や論破という手順不要なのではと思います。
というわけで、論破が存在したとしても日常において必要性ある?という疑問が残ります。
よく目にする論破は非日常的なもの
テレビやYouTubeなどで論破って痛快じゃん!!って思えるような場面たくさんあります。
言わずもがな、あれは非日常的なショーです。演出です。
もしくは、視聴者に働きかけることを目的にしていて、少なくとも論破した相手に行動してもらおうとは考えていません。
一方、我々の日常における議論は参加者含め、次の行動があるのが前提であることがほとんど。
意見がぶつかる時はあるにせよ、相手を言い負かす必要性はありません。
余計な感情の波風が次の行動の妨げになり得るからです。
非日常と日常で行われる行動は論破に限らない話ですが、その目的が全然違うことって結構あります。
上辺だけで判断すると期待通りの効果は得られないかもしれません。
とはいえ、時に意見がぶつかり合う時はあるでしょう。
そんな時はどうするかというと、私は課題を中心において議論を進めればいいのではと考えています。
議論の中心は相手でもなく自分でもなく課題
相手を否定せず、自分も否定せず、という議論があれば平和だなぁって気もしますが、実際そんな議論では議論する意味がありません。
議論によって個々の意見より良い答えが導き出せればやった甲斐があるってものです。
したがって、議論において意見がぶつかり合うことは避けられません。
じゃあ、論破が必要じゃんとなるのは早計です。
なぜなら議論の中心は常に課題だから。
課題に対してどの意見がより効果的か、より近いか、課題を中心に据えて議論すれば、直接的に相手を否定する場面は出てきません。
あくまで今回の課題に対して相手の意見は有効性が低かったという話であって、意見そのものの否定をする必要はありません。先述の通り絶対的に正しいものってないはずですし。
また、主語が相手か課題かで残る感情は違います。
よく日本人は議論になれていなくて感情的になりやすいという話を聞きます。そういう傾向はあるのかもしれませんが、海外でも全くないわけではありません。
英語でも直接的に否定するのが憚れる時は、結果や物を主語にした受動態で表現し「誰」という部分をぼやかす方法は割と観測できます。円滑にことを進めるには感情は大事という認識は世界共通のようです。
議論の主たる目的は課題解決です。
最優先事項はベストな解決策を見つけることですし、相手は言い負かすべき存在ではなく一緒に考える存在だと考えられます。
負かさなきゃいけない相手って課題の方なんじゃないかと思う次第です。
以上、最後までありがとうございます。